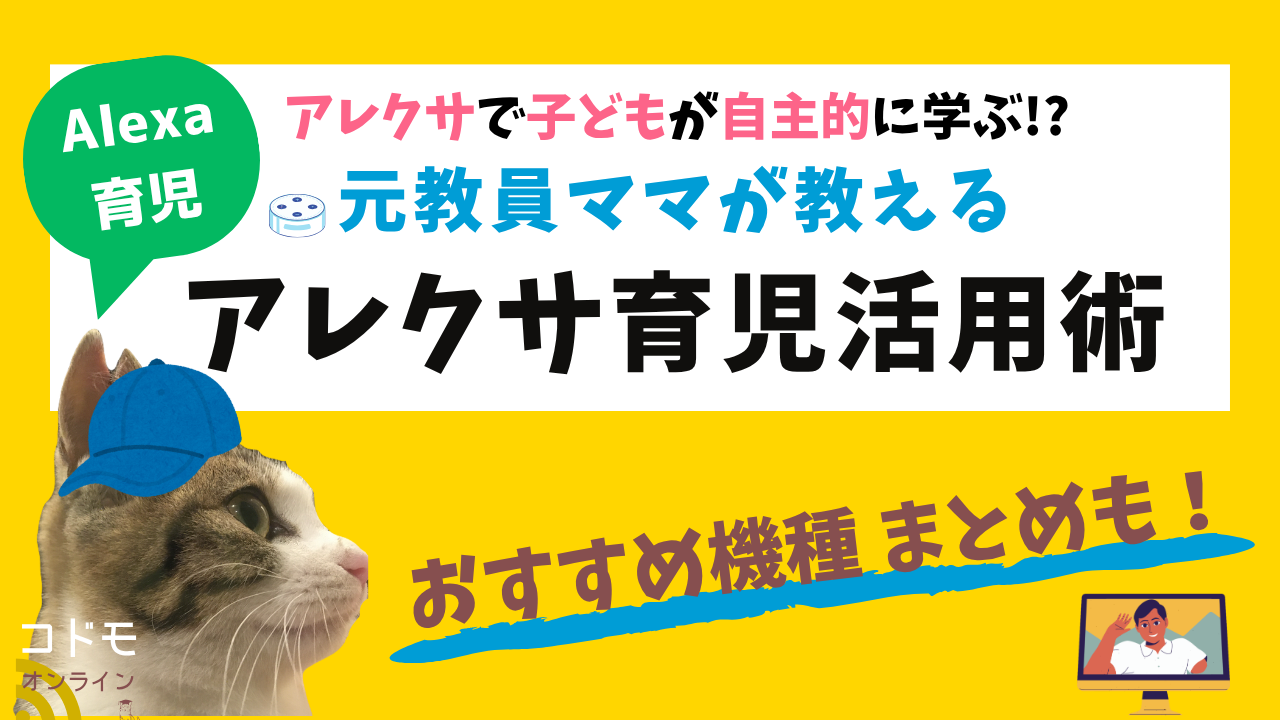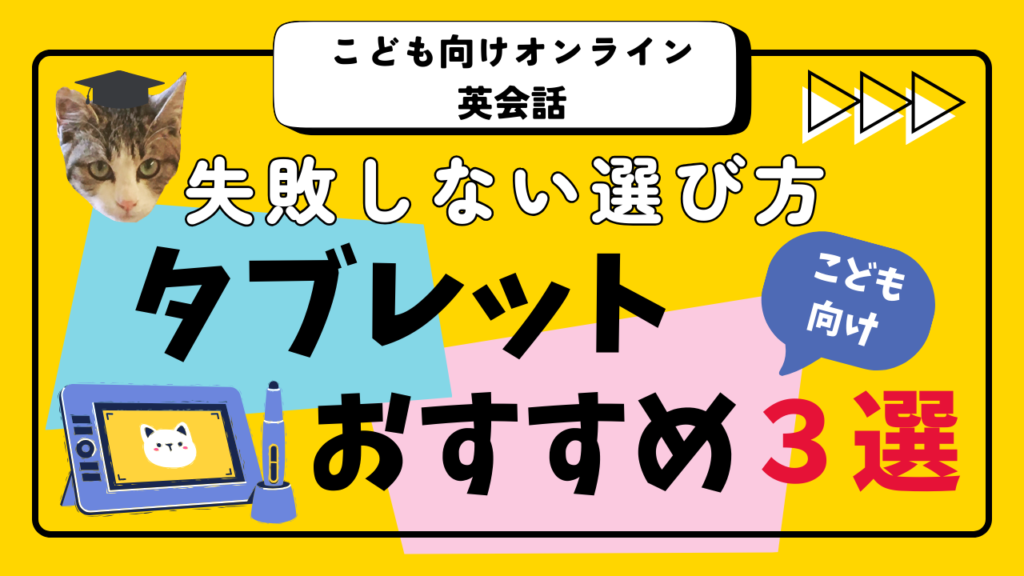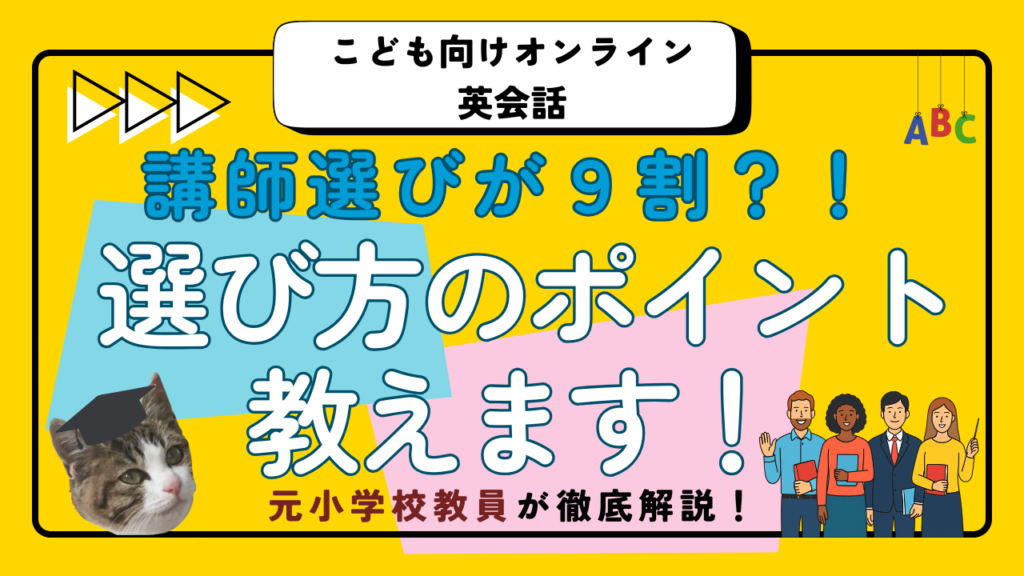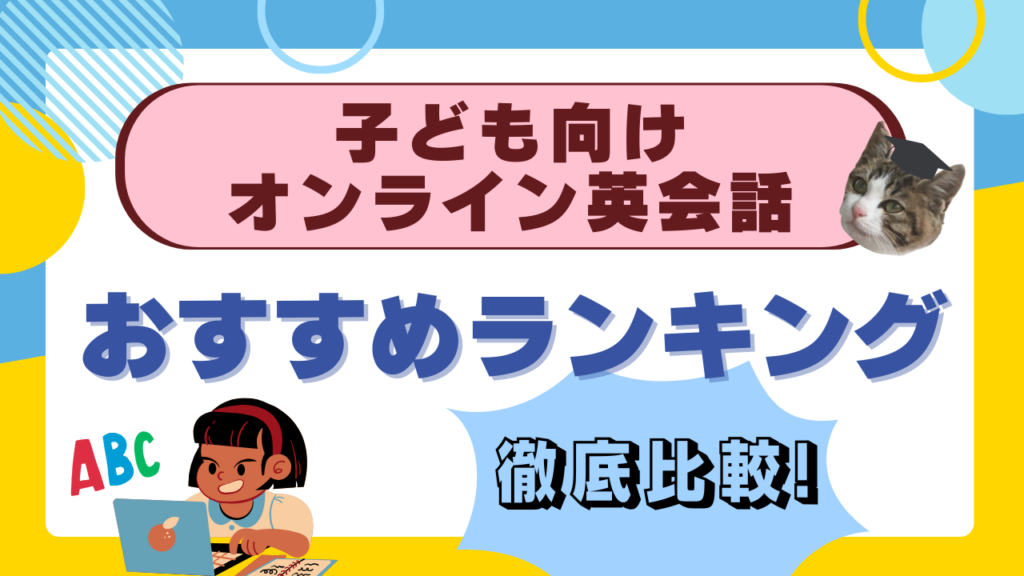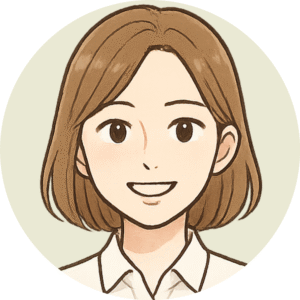「毎日毎日、宿題をさせるのがもう嫌…!」
小1になって急に増えた“やるべきこと”に、毎日声を荒げていませんか?
時間割の準備、宿題、習い事…
全部ママが指示しないと動かない―。
共働き家庭にとって、いわゆる「小1の壁」は想像以上に大きなハードルです。
過去に小学1年生を担任したこともある筆者ですら、この壁に直面し苦労しました。
ところが1学期も中頃、我が家のアレクサの設定を見直してもっと生活に深く入れ込んだことで、子どもの自立がグンと進んだのです。
この記事では、忙しいご家庭でも実践できる「子どもの自立と学びをサポートするアレクサ活用方法」を、筆者の実践事例を交えてご紹介します。
アレクサ活用歴3年以上の筆者が、アレクサの設定方法からご家庭に合うAmazonデバイスの機種選びまで網羅しています。
アレクサには、毎日の「声かけ育児」から少しだけ解放されたいママパパの強い味方になってもらいましょう!
 Jyuni先生
Jyuni先生アレクサは子どもの“できた!”を増やす最強の育児サポーターです。
「小1の壁」とは?
「小1の壁」とは、子どもが小学校に入学する際、特に共働き家庭が直面しやすいさまざまな課題のことを指します。
- 学校の準備、宿題、習い事のスケジュール管理
- 仕事と育児の両立問題
- 忙しい朝・夕方に追われる毎日
- 子どもの行きしぶり
保育園時代と比べて小学校の預かり時間は短くなり、学童保育の定員不足や終了時間の早さなどによって仕事と育児の両立が難しくなるケースが増えます。
このような変化に備えるためには、家庭内での役割分担の見直しや、柔軟な働き方の導入、地域のサポートサービスの活用など、事前の準備と工夫が欠かせません。
一方、子どもにとっての「小1の壁」とは、生活環境の激変による心身の負担の増加です。
- 「決まった時間に登校する」
- 「45分間座って話を聞く」
- 「宿題をこなす」
- 「持ち物を自分で管理する」
このように突然“できて当たり前”になることが増え、ストレスを感じる子も少なくありません。
新しい友だちや先生との関わりも始まり、疲れや不安、癇癪といったサインが表れることもあります。
まさに今「小1の壁」を乗り越えてきた筆者の経験から、アレクサを使った日常生活でのちょっとした工夫をご紹介していきます。
アレクサのここが育児におすすめ!
アレクサを共働き家庭の“育児サポーター”に推薦したい3つの理由が以下。
① 音声で指示・反応してくれる


まず1番の利点は「声」で指示ができること。
1年生どころか未就園児の子どもでも、アレクサを声で操作することができます。
「九九を聞かせて」「物語を読んで」といったリクエストにも応じてくれるため、遊び感覚で学びに取り組むことができるのも大きな魅力です。



我が家ではよく子どもたちとアレクサとの「しりとり」や「じゃんけん」大会が繰り広げられています。
② スケジュール管理の自動化


小学生になったばかりの子どもには「言われないとできない」ことが多く、親の声かけや見守りが欠かせません。
しかし、忙しい朝や仕事終わりに毎回同じことを言うのは、親にとっても大きな負担ですよね。
そんなとき、音声アシスタントのアレクサがあれば、その負担をグッと軽減できます。
たとえば、「7時に起きる」「宿題を始める」「お風呂の時間」など、子どもの生活習慣をリマインダーで自動化できます。
こうしてスケジュール管理を自動化してしまえば、お子様への細かい声掛けが不要になっていきます。
③ スマート家電との連携
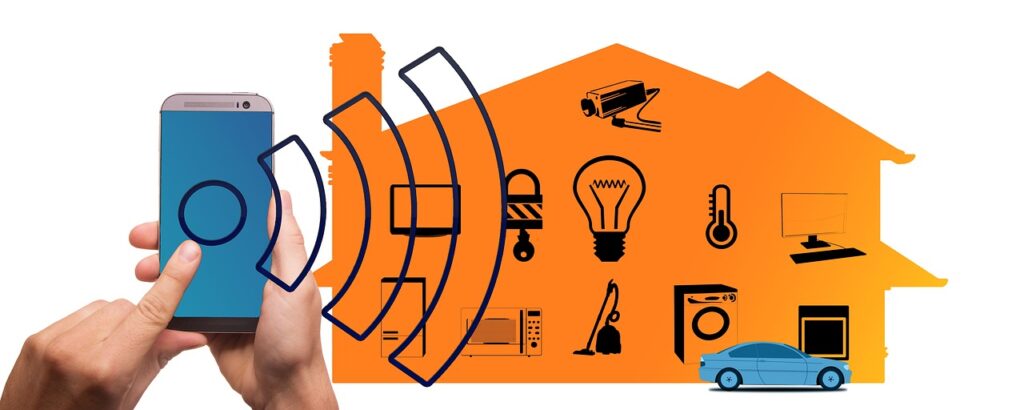
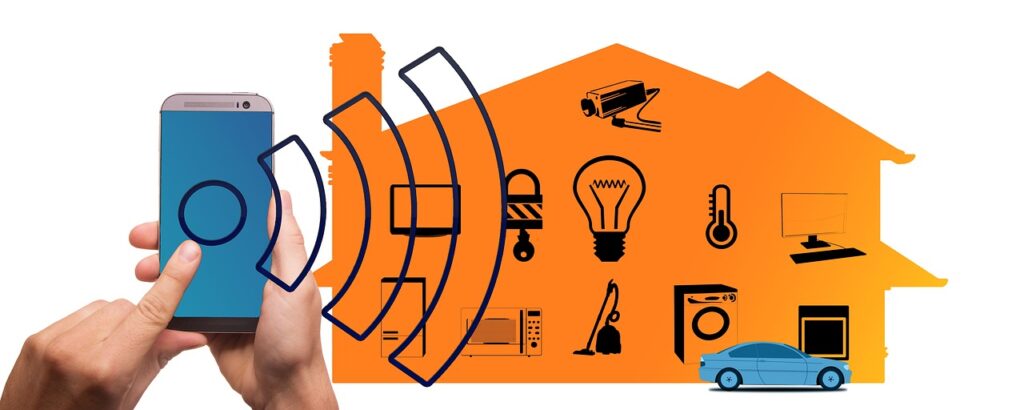
また、スマート家電との連携を使えば、親が手を離せないときでも照明やテレビの操作ができ、家事の時短にもつながります。
設定さえしておくと「アレクサ、おはよう」と言えば、カーテンが自動で開き、今日の天気を知らせてくれ、電気が付き、テレビやエアコンが付く。
大人にとってはこの家電の一連の動きを自動化できることが一番衝撃的でしょう。
正直もうアレクサがいなかった時の生活に戻れません。
このように、アレクサは“声かけ・生活管理・学び”の3つの役割を担ってくれる、共働き家庭の強い味方なのです。
上手に活用すれば、親子のイライラを減らし、自立をうながすツールになりますよ。



今回はおもに①と②について詳しく解説していきます!
おすすめのアレクサ育児活用例
さっそくおすすめのアレクサの育児活用例を3つ紹介します。
我が家はリビングにアレクサ「Echo Show(エコーショー)」を設置しています。
「Echo Show(エコーショー)」は音声操作に加え、画面で天気やニュース、動画やビデオ通話なども楽しめるオールマイティーな機能が特徴。
上位モデルであれば、より画面が大きく液晶が綺麗だったりします。
時間やタイマーなども視覚的に分かりやすいのでお子様にも使いやすいシリーズです。


他にも寝室や洗面所にもアレクサの他シリーズを設置していますが、詳しくは後述しますね。



そんな我が家のアレクサの活用方法の一部をご紹介します。
①ルーティンのリマインダー活用
小学校に入ると、朝の支度が一気に増えてバタバタしがち。
そんなときに頼りになるのが、アレクサの「リマインダー機能」です。
アレクサのリマインダー機能は、「音声操作」と「アプリ操作」の両方で簡単に設定できます。
「アレクサ、朝7時30分に【ハンカチ持った?】をリマインドして」
と話しかけるだけで、指定した日時・内容でリマインダーが登録されます。
また、アレクサアプリを使うと以下のような画面で設定もできます。


ちなみにこの設定だと…
月曜から金曜は毎日、15:30に
【宿題のじかんだよ】
とアレクサが呼びかけてくれます。
「Echo Show(エコーショー)」はタッチパネルの画面付きなので、繰り返し設定も音声とタッチパネルで指定可能です。
たとえば、朝7時に
【おはよう!トイレに行こう!】
とアレクサが声をかけてくれるだけで、子どもは次にやるべきことを自分で思い出すきっかけになります。
さらに、前述した設定のように
毎朝7時30分に【ハンカチ持った?】
と確認してくれるように設定すれば、忘れ物防止にもつながります。
毎日同じ時間に同じ内容を伝えてくれることで、親が何度も声かけをしなくても、子どもの中に自然と朝の習慣が身についていくのです。



もちろん、初めのうちは中々子ども一人では動けません。
その際は大人が一緒に手伝ってあげてくださいね。
②タイマー機能を併せた設定
学校から帰ってきたあと、「宿題やったの?」「まだやってないの?」と何度も声をかける毎日に疲れていませんか?
そして必ずこんな言葉が返ってくるでしょう。
「今やろうと思ってたのに!」
「もうやる気なくなった。」
そんな場面で役立つのが、アレクサによる“学習の時間割り”です。
たとえば、先ほどのリマインダー機能で
16時に【宿題の時間だよ】
とアレクサが知らせてくれるように設定すれば、子ども自身が「今やる時間なんだ」と気づけるようになります。
さらに
「5分間計算問題をやってみよう」
「音読の時間だよ」
など、アレクサの声かけで学習内容を細かく区切ることも可能です。
「アレクサタイマーを15分計って!」→ 15分タイマー
このようにタイマー機能と組み合わせれば、集中力が続かない子にも取り組みやすく、学習習慣を少しずつ育てることができます。



家庭やお子様の状況によって、一番スムーズな流れを試してみてください。
③ 子どもが自ら学びに活かす
子どもの学びに役立つアレクサの使い方として、特におすすめなのが「辞書」「読み聞かせ」や「学習ソング」の機能です。
たとえば、
「アレクサ、”中秋の名月”って何?」
「アレクサ、昔話を読んで」
「アレクサ、九九の歌かけて」
この呼びかけだけで、お子様が自分でアレクサを操作することができます。
アレクサでは「九九の歌」などの学習ソングや昔話の読み聞かせ、英語のリスニング、クイズ形式のキッズスキルなど、耳から学べるコンテンツが充実しています。
耳からの学習(聴覚学習)は、理解力や記憶の定着に効果的とされているのはご存知の方も多いかと思います。
たとえば「オーディオラーニングは読書より記憶に残りやすい」という研究報告もあり、特に音とリズムを活用した学習(例:九九の歌)は、子どもにとって効果的なインプット方法です。
手が離せないときでも、遊び感覚で学習でき、語彙力・記憶力の向上にも役立ちますよ。



特に九九の歌は一年生から聞いておいても良いくらい!
BGMとして流しておくだけでも勝手に頭に入ってしまいます。
さらに、アレクサには子ども向けに設計された「キッズスキル」という専用機能があります。
これは、教育系・遊び系のスキル(=アプリのようなもの)を追加して、より幅広いコンテンツが使えるようになるものです。
これらは一度「スキルを有効にする」だけで、後は声で呼びかけるだけでOK。
「アレクサ、【なぞなぞランド】を開いて」
と言えば、すぐ始められます。
- さんすうクイズ:小学生向けの計算問題をランダムに出題
- 英単語であそぼう:英語の単語とその意味をクイズ形式で学べる
- なぞなぞランド:親子で楽しめるなぞなぞを出題



まずはここまでの3つの使い方を是非試してみてくださいね!
子ども向けのアレクサ安心設定
「アレクサって小さな子どもでも声で簡単に操作できちゃうから逆に怖くない?」
そう感じている親御さんもきっと多いでしょう。
そこで次の子ども向けのアレクサ安心設定の方法を詳しく解説しますよ。
アレクサには、このような子どもが安全に楽しく利用するための様々な機能が備わっています。
これらの機能を活用し、育児や家庭学習に役立てていきましょう。



是非次の設定を参考にしてみてください!
子ども用プロフィールの設定方法
まず最初に行っていただきたいのが、お子様専用のプロフィールの作成です。
デバイスごとにこれを行うことで、その子に合わせた設定やコンテンツ管理が可能になります。
スマートフォンにインストールされているAlexaアプリを開く。
「設定」をタップし、さらに「プロフィールと家族」へ進む。
ここでお子様の名前と年齢を入力。
この手順でお子様専用のプロフィールが作成されます。
このプロフィールをEchoデバイスに紐づけることで、様々な制限が適用されるようになるのでお子様の成長に合わせて以下についても管理できるようになります。



年齢を設定しておくだけでアレクサが色々判断してくれるよ!
音量・使用時間のコントロール
「アレクサの音が大きすぎる」「アレクサばかり使って宿題が進まない」といった心配も、以下の設定で解決できます。
音量制限の設定
子ども用プロフィールに紐づけたEchoデバイスでは、最大音量を設定できます。
我が家でもありましたが、好きな音楽を大音量で聴く…そういったことを防げます。
使用時間制限の設定方法
Fireキッズモデルと同様に、アレクサでも使用時間制限を設定できます。
Echo Show(エコーショー)シリーズを子供部屋に置いている場合などには動画の見過ぎといった問題を防げます。
「その他」→「設定」→「アカウント設定」→「子ども用プロフィール」から、設定したいお子様のプロフィールを選びます。
ここで「一日の制限時間」や「おやすみ時間」を設定できます。例えば、「平日は1時間まで」「夜8時以降は使用不可」といった設定が可能。
どのEchoデバイスで使用時間を制限するかを選択します。



特に子ども部屋のデバイスには設定しておきたいですね。
有害コンテンツブロック・購入制限
子どもに不適切なコンテンツへのアクセスや、意図しない購入を防ぐための重要な設定です。
有害コンテンツのブロック設定方法
前述した子ども用プロフィールでは、初期設定で不適切なスキルや音楽、ニュースなどがブロックされる機能が備わっています。
お子様のプロフィール設定画面を開きます。
ここで、お子様が利用できるスキルやコンテンツを個別に許可したり、ブロックしたりすることができます。
Amazon Kids+(プライム会員:月額580円)を利用すると、年齢に応じた厳選されたコンテンツ(絵本、学習アプリ、動画など)のみにアクセスを制限できます。



「Amazon Kids+」は主にキッズ向けタブレットなどのデバイスで利用されることが多いです。
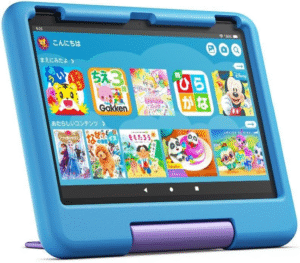
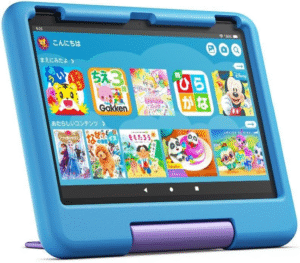
音声での購入制限
子どもが「アレクサ、〇〇を買って」と誤って注文してしまうのを防ぐための設定です。
「その他」→「設定」へ進む。
これで、音声での購入ができなくなります。
もし、家族の誰かが音声での購入を利用する場合は、「音声ショッピングのPIN」を設定することで、PINコードを知っている人しか購入できないようにすることも可能です



筆者的には音声での購入設定は常時OFFにしておいて良いと思います。
我が家では実際に、アレクサからの提案で子どもが「はい」と答えてしまって購入キャンセルしたことも…
Amazon Echo(アマゾンエコー)の種類と場所別おすすめ機種
Amazon Echo(アレクサ対応のAmazonデバイス)は、用途や設置場所に合わせてさまざまなモデルが展開されています。
子育て中のご家庭では、使用シーンや部屋の用途などによって最適な機種を選ぶことで、より快適にアレクサの機能を活用できます。
種類別おすすめの設置場所
以下に筆者の使用感と併せておすすめできる設置場所について紹介します。
Echo Dot(エコードット)


おすすめの場所:玄関・寝室


コンパクトサイズながら音質も良好で、アレクサの基本操作はすべて可能。
音声で絵本を読んだり、アラームやタイマーをセットしたりするのにぴったりです。
価格もリーズナブルなので導入しやすいのが特徴。
Echo Pop(エコーポップ)


おすすめの場所:子ども部屋・寝室
ポップなデザインとコンパクトサイズで、インテリアになじみやすいモデル。
画面がないので寝室で使用してもそこまでライトが気になりません。
子ども部屋用や、玄関でスマート家電の操作をしたり、天気や予定をチェックしたりするなど、ちょっとした使用に最適です。
Echo Spot(エコースポット)


おすすめの場所:洗面所・子供部屋
丸型でコンパクトなスクリーンを備えた最新モデル。
音声操作はもちろん、天気予報やニュース、時計などの情報を画面で確認できる点が大きな特徴です。
画面サイズが小さめで場所を取らず、情報確認やビデオ通話を手軽に行いたい人に最適なモデルです。
Echo Show(エコーショー)シリーズ


おすすめの場所:リビング・ダイニング
タッチスクリーン付きで、ビデオ通話や動画視聴が可能。
大きくタイマーを表示したり、天気や予定を一目で確認できるため、家族が集まる場所での使用に向いています。
子ども向けスキルも視覚的に楽しめます。



Amazonデバイスには、更に細かく分けると画面が大きいモデルや大きさが違ったモデルがあります。
ここでは筆者が使いやすいと思うモデルをご紹介しました。
さらに詳しく比較したい方は以下の表をご覧ください。
Amazon Echo 機種別比較!
| 製品名 | 製品 | 商品ページ | 価格 | 特徴・機能 | サイズ | 設置 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Echo Dot (第5世代) |   | Amazonで見る | 7,480円 | コンパクト&高性能 読み聞かせ・クイズ学習に◎ | 小型 | 玄関 寝室 |
| Echo Pop |   | Amazonで見る | 5,980円 | コンパクト 音声操作 安価 初めての方に | 超 小型 | 寝室 子供部屋 |
| Echo Spot (2024新型) |   | Amazonで見る | 11,480円 | スマート目覚まし 時間・天気表示 音声操作 | 超 小型 | 洗面所 子供部屋 |
| Echo Show5 (第3世代) |   | Amazonで見る | 12,980円 | 小型画面付き 動画・ビデオ通話・カレンダー表示可 | 中型 | リビング |
| Echo Show 8 (2024新型) |   | Amazonで見る | 22,980円 | 大画面で家族共用◎ 動画視聴や予定管理 | 大型 | リビング |
| Echo (第4世代) |   | Amazonで見る | 11,980円 | バランス型 Dotより大きい Dotより高音質 | 中型 | 寝室 リビング |
※価格は2025年6月現在



Amazonセールなどを狙えば40%オフなど半額近い値段で買えるのでおすすめ!
アレクサ育児 ここだけ注意!
ご紹介してきたようにアレクサは育児に便利なツールですが、すべての家庭に万能というわけではありません。
実際にアレクサを3年程使ってきた筆者が、アレクサを育児に取り入れる際の注意点についてもお伝えしておきたいと思います。
ご家庭の状況に合わせて、上手に活用できるか見極める参考にしてください。
デジタル機器全般に抵抗がある
「子どもにはなるべくデジタル機器を使わせたくない」
「家族との直接的なコミュニケーションを重視したい」
こういった考えが強い場合、アレクサの導入は抵抗を感じるかもしれません。
無理に導入しても、ストレスを感じてしまう可能性があります。
ご家庭の教育方針や価値観を大切にすることが一番です。
家庭でのルールがまだ曖昧
「使用時間は?」
「どんな時に使うの?」
こんな風にデジタル機器に関する家庭内のルールがまだ明確でない場合、アレクサを導入することで、かえって混乱を招く可能性があります。
まずは、家族で話し合い、デジタル機器との付き合い方について具体的なルールを決めてから検討することをおすすめします。
ルールが定まっていないと、アレクサの便利な機能も十分に活かせないかもしれません。



ご自身のライフスタイルや教育方針、お子様の性格などを考慮し、上手に活用できるかどうかを考えてみてくださいね。


「オンライン学習」でさらに一歩!
ここまでは、アレクサを使った育児への活用方法等をご紹介しました。
しかし、アレクサの可能性はそれだけではありません。



小学1年生のお子様の「学び」をさらに深めるために、筆者はオンライン学習ツールとの併用をおすすめしています。
オンライン学習は、自宅で自分のペースで進められるのがメリットですが、その分、計画的に進めるのが難しいところがデメリット。
「スタディサプリ」のようなオンライン学習は、学校の授業の予習・復習や苦手克服にとても効果的です。
これにアレクサを組み合わせることで、学習習慣の定着をよりスムーズに促せます。
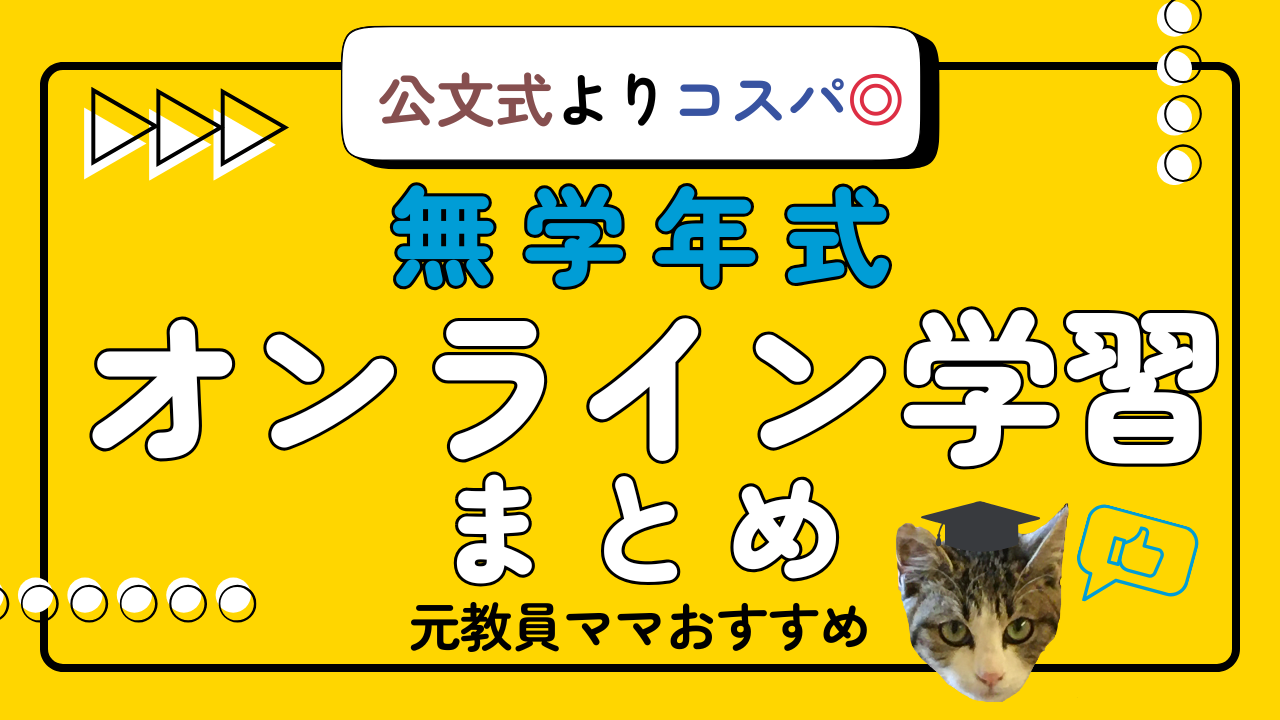
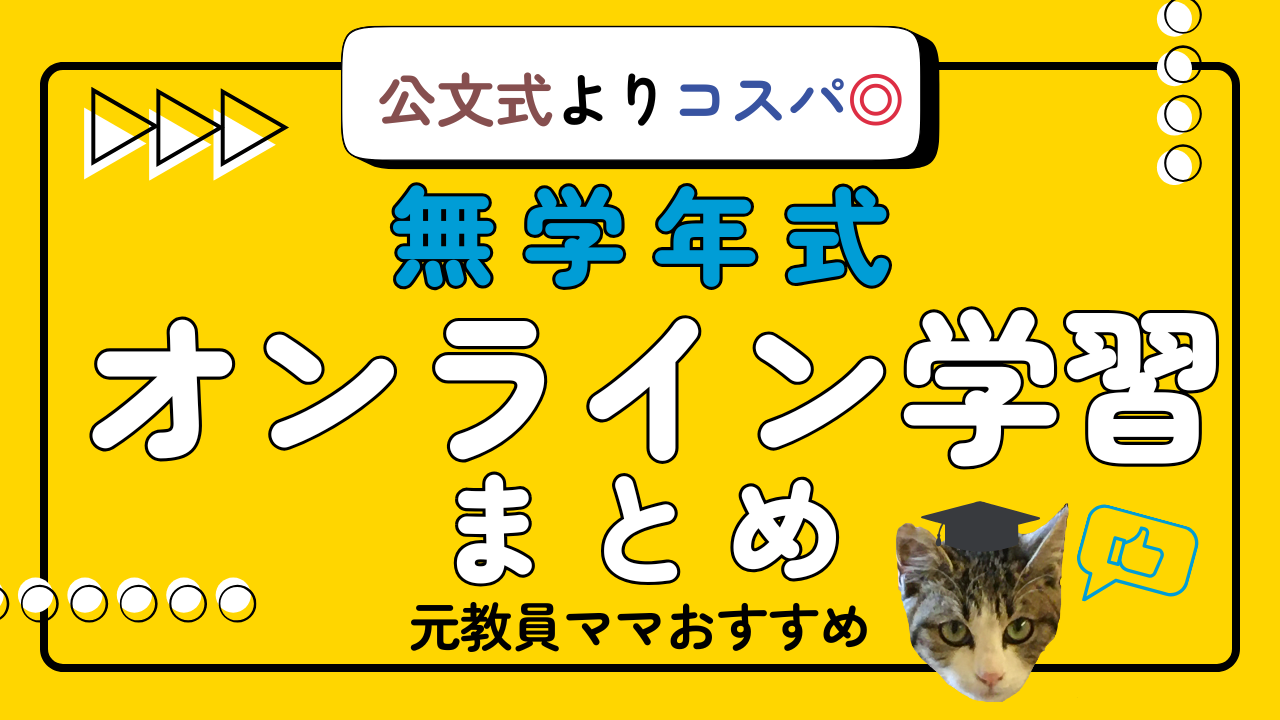
例えば、以下のように活用します。
ルーティン設定で学習習慣化
「毎日〇時に、【今日はスタディサプリの国語の学習を頑張ろうね】とリマインド」
このようなルーティンを設定すれば、決まった時間に学習に取り組む習慣がつきやすくなります。
「アレクサ、20分タイマーをセットして」
集中して取り組むためには時間管理が大切。
アレクサにタイマーを設定させることで、子どもが時間を意識して勉強する力を自然と身につけられます。
このように、アレクサは自主学習を円滑に進めるための「育児サポーター」となり、オンライン学習ととても相性が良いのです。
まとめ 〜「アレクサ」は“時短”で“自立”を育てる味方!〜
「アレクサに子育てを任せるなんて、機械的だし甘えじゃない?」
と感じる方もいるかもしれません。
でも、共働きの元小学校教員であり、2児の母でもある私からはっきり言わせてください。
それは決して甘えではありません。
むしろ、アレクサは忙しいママ・パパにとっての“時短ツール”であり、子どもの“自立心”を育てるための強力なサポーターです。
親がすべてを先回りして指示するのではなく、アレクサが【時間だよ】【次は何する?】とシンプルに声をかけることで、子どもは自分で考え、行動する力を自然と身につけていきます。
自己管理のできる子ならアレクサを自分で使いこなしてリマインドする子もいるでしょう。
その結果、親には時間的・精神的なゆとりが生まれ、本当に向き合いたいときに、より深く関わることができるようになるのです。
忙しい毎日だからこそ、少しの工夫とテクノロジーの力を借りて、子どもが「自分でできる」ことを積み重ねていきましょう。



AIやスマートデバイスを自分で使いこなす力は、これからの時代を生きるうえで欠かせないスキルになっていくでしょう。
勿論全ての子どもにこの方法が合うわけではありません。
毎日の宿題に行き詰まっているママは、まずは手軽に始められるAmazonデバイスからご家庭に取り入れてみませんか?
| 製品名 | 製品 | 商品ページ | 価格 | 特徴・機能 | サイズ | 設置 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Echo Dot (第5世代) |   | Amazonで見る | 7,480円 | コンパクト&高性能 読み聞かせ・クイズ学習に◎ | 小型 | 玄関 寝室 |
| Echo Pop |   | Amazonで見る | 5,980円 | コンパクト 音声操作 安価 初めての方に | 超 小型 | 寝室 子供部屋 |
| Echo Spot (2024新型) |   | Amazonで見る | 11,480円 | スマート目覚まし 時間・天気表示 音声操作 | 超 小型 | 洗面所 子供部屋 |
| Echo Show5 (第3世代) |   | Amazonで見る | 12,980円 | 小型画面付き 動画・ビデオ通話・カレンダー表示可 | 中型 | リビング |
| Echo Show 8 (2024新型) |   | Amazonで見る | 22,980円 | 大画面で家族共用◎ 動画視聴や予定管理 | 大型 | リビング |
| Echo (第4世代) |   | Amazonで見る | 11,980円 | バランス型 Dotより大きい Dotより高音質 | 中型 | 寝室 リビング |